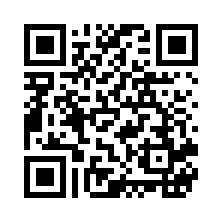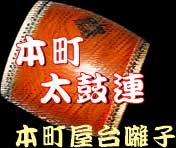




 |
秩父神社には、12月2・3日の秩父祭と7月19・20日の川瀬祭があります。 この二つの祭礼で屋台・笠鉾・山車を曳き回す時に演奏されるのが祭囃子です。
この二つの祭礼で屋台・笠鉾・山車を曳き回す時に演奏されるのが祭囃子です。この祭囃子は、秩父祭と川瀬祭の両方に共通した曲目であり、これは、小太鼓のリズムを基本として鉦・笛・大太鼓を合わせた音楽であり、 屋台等の曳き手の士気を高めるために演奏されます。 大太鼓の叩き手が大太鼓のこばを撥でカカッと叩いてからドドド・・・と叩き出す 小太鼓がテレテッケのリズムを叩きはじめる 大太鼓は小太鼓のリズムに乗って、大波・小波・ドコン・つなぎのリズムを演奏 鉦は小太鼓と同じリズムを担当 時に装飾音を入れる 笛は大太鼓と律動的にからみ、大太鼓のリズムを引き立て先導 |
 |
||||||||||||||
|